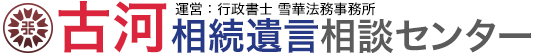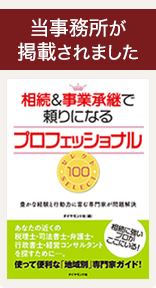行方不明の相続人(失踪宣告)について
相続手続きにおいて、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。一人でも相続人が不在の場合、その遺産分割協議は無効となります。相続人の中に行方不明の人がいると遺産分割協議を進めることができなくなります。
では、相続人の中に行方不明者がいる場合どうしたらよいのでしょうか。この場合は、行方不明人の代理者をたて、不在者財産管理人の選任によって遺産分割協議を進めることが可能になります。また、行方不明となってから原則7年以上経過している場合は、失踪宣告という、生死が分からない状況の人に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じされる制度があります。失踪宣告の手続きによって、行方不明者を相続人から除外することができ、遺産分割協議を進めることが可能になります。
失踪宣告
失踪宣告を受けると死亡したものとみなされますが、いつ死亡したものとみなされるかは、普通失踪と特別失踪とで異なります。
普通失踪
生死が7年間以上明らかでない場合、普通失踪といいます。行方の分からないまま7年が経過したら自動的に死亡したとみなされるというわけではなく、親族などの利害関係者が、家庭裁判所へと失踪宣告申立てをします。そこではじめて法律上、行方不明者が死亡したとみなされます。この場合、死亡日は行方不明になってから7年が満了した時点となります。
特別失踪(危難失踪)
死亡の原因となりうる危難(地震や火災、戦地へ臨んだ、沈没した船舶に乗船していた等)に遭遇した人が、その危難が経過した後、1年しても生死不明である場合に認められる失踪宣告を特別失踪(危難失踪)といいます。普通宣告と同様、利害関係者が家庭裁判所へと申立てを行い、失踪が宣告されます。この場合の死亡日は、危難が去った時点となります。
行方不明者が見つかった場合、失踪宣告は取り消し可能
もし、失踪宣告を受けた人が生きていた場合や、失踪宣告による死亡時とは異なるときに死亡が判明した場合は、失踪宣告は取り消す事ができます。
失踪宣告を取り消すと、すでに受け取った相続財産、死亡保険金等について、失踪宣告を取り消した場合はどうなってしまうのでしょうか。この場合、すでに相続人が受け取った財産については行方不明者へと返還しなければなりませんが、分割済で、手元にないものについては請求をする事は出来ません。保険金に関しても、使用済みの保険金については返還する必要はなく、手元に残っている保険金についてのみ保険会社へと返還します。失踪宣告の取り消しは、本人か利害関係者が申立てをします。
以上、失踪宣告について説明しました。失踪宣告は必要な制度ですが、複雑で困難な手続きです。このような状況でお困りの古河のお客様は、すぐに専門家へと相談し解決してもらいましょう。古河相続遺言相談センターでは、行方不明者がいる場合の相続手続きについてのサポート体制も整えております。古河近郊にお住まい、または古河近郊にお勤めの皆様の相続についてのご不安ご質問などは、初回ご相談無料の古河相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
相続手続きについての関連項目
「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました

当センターを運営しております 行政書士 雪華法務事務所 がダイヤモンド社「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に掲載されました。
まずはお気軽にお電話ください
0280-33-3685
営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。